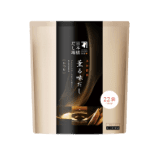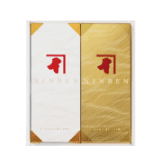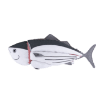兵庫のおいしい郷土料理の厳選30選!特徴や味付けのポイントも紹介
最終更新日:
公開日:

兵庫の郷土料理といえば明石焼きや神戸牛を使った料理が有名ですが、他にもたくさん思いつくという人は少ないかもしれません。
『古事記』によると、イザナミとイザナギの2人の神様が最初に作ったのが、瀬戸内海に浮かぶ淡路島とされています。「天皇の食膳の海産物を奉仕する土地」といわれ、日本海と瀬戸内海に囲まれた兵庫は海の幸が豊富です。
しかし、兵庫は但馬牛のような畜産物や丹波の黒豆をはじめとした農産物も多く、素材を活かした郷土料理がたくさんあります。
この記事では、兵庫のおいしい郷土料理を30選紹介します。自宅で兵庫の郷土料理を作ってみたい人のために味付けのポイントも解説します。
兵庫の郷土料理に関心がある人は、ぜひ参考にしてください。
兵庫のおいしい郷土料理30選!

兵庫の郷土料理30選を紹介します。
全て読むのが大変な場合は、興味がある料理だけでも読んでみてください。
明石焼き
明石焼きは明石市の代表的な郷土料理で、小麦粉に「じん粉」、卵、だし汁を混ぜた生地にタコを入れて焼き、かつおや昆布のだし汁に浸して食べます。
「じん粉」とは小麦粉からグルテンを取り除いて、残ったデンプンを精製して作られたものです。「浮き粉」や「貫雪粉(かんせつこ)」などとも呼ばれます。
たこ焼きはネギや生姜などを入れてソースをつけて食べますが、明石焼きは具材はタコのみでだし汁に浸して食べるのがたこ焼きとの大きな違いです。
昔は地元では「卵焼き」と呼ばれていましたが、市の職員が明石のPRのために明石焼きと名付けたところ、全国に広まったとされています。
黒豆煮
兵庫の丹波篠山市に伝わる黒豆煮は、乾燥した黒大豆を水で戻して、砂糖や醤油などで弱火でじっくり煮詰めた料理で、古くから正月のおせち料理の一品として親しまれています。
丹波篠山の黒大豆は、粘土質で肥沃な土と昼夜の寒暖差で糖度が高く粒も大きいため、黒大豆の最高級の品質といわれ全国的に有名です。
近年は健康ブームで黒大豆に含まれるポリフェノールが注目されて、正月だけでなく一年中食べられるようになっています。
丹波黒豆ごはん
丹波黒豆ごはんは丹波篠山の黒大豆を水に浸して戻し、塩と酒で味を整えて一緒に米と炊いたものです。
丹波篠山の黒大豆は粒が大きくて糖度が高いことから、黒大豆のなかでは最高級品質といわれ、皮が破れにくい特長もあります。
黒豆ごはんは田んぼの苗の成長を祈願し6月に行われる「さびらき(早苗開き)」で、おにぎりのように丸めて田の神に供えていました。現在でも田植えや祝い事、法事などの行事では黒豆ごはんが炊かれ、学校給食でも提供されています。
ぼたん鍋
ぼたん鍋は味噌ベースのだし汁に猪肉を入れて作る鍋料理で、丹波篠山市の郷土料理です。
発祥は1908年(明治41年)ごろ、多紀郡篠山町で訓練中だった陸軍が捕獲したイノシシを味噌汁に入れて食べたことからとされており、当初は「いの鍋」と呼ばれていました。
「ぼたん鍋」という名は昭和になってから、猪肉を「ぼたん」と呼ぶことから付いたもので、ぼたんと呼ぶようになった由来は「肉が紫紅色でボタンの花に似ているから」といわれています。
正月料理としてや、来客をもてなすために提供されるごちそうです。
鍛冶屋鍋
鍛冶屋鍋は日本で最初の金物の町として知られる、三木市に伝わる郷土料理です。
だし汁に酒やみりん、醤油などの調味料を合わせて煮立たせ、タコとなすを入れて煮込んだもので、鍛冶職人が夏に精力をつけるために食べたといわれています。
明治から大正時代には、明石沖でとれたタコと夏が旬のなすで作られた鍛冶屋鍋は、火を使って火照った鍛冶職人の体を冷やすと喜ばれました。
一時期は廃れ、1990年ごろから見直されて復活しましたが、三木市内の飲食店で提供されているところはないといわれています。
いかなごのくぎ煮
いかなごのくぎ煮はイカナゴの稚魚(新子)を甘辛く佃煮にしたものです。「くぎ煮」とは煮上がった姿が、さびたくぎが曲がったように見えることから呼ばれています。
毎年2月末から4月、イカナゴの稚魚を採る新子漁が行われ、地元では瀬戸内の春の風物詩になっています。
元々は神戸が発祥とされる漁業関係者の家庭料理で、1980年以降、家庭向けにレシピを改良し一般に広く知られるようになりました。現在は家庭で作られるほか、土産物屋、スーパーなどで購入できます。
神戸牛ステーキ
「神戸牛」は言わずと知れた高級ブランド牛ですが、この神戸牛を鉄板の上で塩とこしょうで味付けて焼き、ステーキソースや辛子をつけて食べる神戸牛ステーキも世界的に知られています。
神戸牛とは「但馬牛(たじまうし)」のことで、但馬牛のなかの厳格な基準を満たしたものが「神戸牛」と呼ばれます。日常食ではなく、特別な日のごちそうとして飲食店で食べることがほとんどです。
明治時代、来日外国人のために神戸港から但馬牛を送ったところ、味がよく非常に好評で神戸牛が広まりました。2015年には国の「地理的表示(GI)保護制度」に神戸牛が登録されています。
姫路おでん
姫路おでんは辛子ではなく、生姜醤油をかけたりつけたりして食べるおでんです。
関東風の濃く甘い味付けのおでんを関西では「関東煮」と呼ぶことが多いです。姫路では関西風の薄味のおでんと関東煮の2種類があり、どちらも生姜醤油を使った「姫路おでん」と呼ばれています。
2006年、「姫路の食で町おこし」活動で「姫路おでん」が命名されてから、ご当地グルメとして広く知られるようになり、姫路おでんを目的に訪れる観光客も多いです。
祭りや棟上げなどの祝いの場でも食べられ、残ったおでんの具を刻んでお好み焼きに入れて食べる家庭もあります。
とふめし
とふめしとは「豆腐めし」のことです。茹でた豆腐やサバの水煮などを炒めて混ぜごはんにしたもので、丹波篠山市の大山地区に約120年前から伝わるとされます。
地域の長老が、大勢の料理を用意するのは大変なので「おかずとごはんを混ぜればいい」と提案したことから生まれたといわれています。若狭湾から京都に魚を運ぶ「鯖街道」がつながっていたため、山里の大山地区でも塩漬けのサバが手に入りました。
江戸時代の農閑期、出稼ぎの弁当にも「とふめし」が詰められていたとされ、現在でも地区の運動会や冠婚葬祭などの集会の際に振る舞われています。
さば寿司
さば寿司は酢でしめた塩サバを使った寿司で、にぎり寿司の他に姿寿司や棒寿司などさまざまな形状があります。
姿寿司はサバの姿そのままの寿司で、棒寿司は頭と尾を除き、酢でしめた半身の塩サバを酢飯にのせて棒状にして竹の皮で包んだものです。
サバは昔、冷蔵技術がなかった時代に若狭湾から京都まで焼いたり塩漬けにしたりして「鯖街道」と呼ばれた街道を使って魚類を運びました。さば寿司に使われたのはこの街道を使って運ばれたサバです。
現在も祭りのときや家庭料理としてさば寿司が作られるほか、飲食店でも販売されています。
さばのじゃう
さばのじゃうはサバと焼き豆腐、白菜やネギなどの野菜などを一緒に煮込んですき焼き風にした寄せ鍋のことです。
但馬地域の漁港がある街の漁師めしとして作られ、小さなサバのほか、商品にならないような雑魚やハタハタなども「じゃう」にしていました。
現在も家庭で作られることもあります。また、地域の料理教室で郷土料理として紹介されることもあるようです。
播州手延べそうめん
播州(ばんしゅう)手延べそうめんという名前ではピンとこなくても、「揖保乃糸」という商品名を知る人は多いのではないでしょうか。
コシがあって食感がよく茹でのびにくいことから、播州そうめん「揖保乃糸」は播磨地方の名産品として全国に広く知られています。
播州は播州平野で収穫される小麦や揖保川の清流、赤穂の塩などそうめん作りの条件が揃い、冬の農閑期の副業にもなったことで、播州そうめんは江戸時代から盛んに作られました。
家庭での普段使いから高級贈答品まで広く対応し、夏は冷たいつゆで、冬は温かいにゅうめんとして一年中食べられています。
出石皿そば
出石(いずし)皿そばは何枚もの出石焼きの小皿にそばが盛られた、豊岡市出石町のユニークな郷土料理です。地元では「箸を立てた高さの分量が成人男性の一人前」といわれます。
出石のそばは300年以上前から改良を重ねながら、挽きたて、打ちたて、茹でたてにこだわって作られ発展してきたそばです。幕末のころ、屋台で提供しやすいように小さな浅い皿にそばを盛ったのが始まりとされています。
出石皿そば協同組合では毎年11月に「新そば祭り」を開催しており、4月には但馬國出石観光協会が「出石そば喰い大会」を実施して普及に努めています。
かつめし
かつめしとは加古川の郷土料理で、皿に盛ったごはんにビーフカツをのせてデミグラスソースをかけ、脇にゆでキャベツを添えたものです。
ビーフカツが珍しかった時代に「ナイフやフォークがないときに箸で気軽に食べられる洋食」として考案され、加古川市やその周辺の飲食店100店以上(2021年時点)で「かつめし」が提供されています。
ビーフカツだけでなく、エビカツやとんかつ、チキンカツを使ったり、デミグラスソース以外のソースをかけたり店ごとに異なるバリエーションを楽しめます。普段の家庭料理や学校給食でも提供されるメニューです。
ぼっかけうどん
「ぼっかけ」とは牛スジ肉とこんにゃくをだし汁で煮込んだもので、「ぶっかける」が語源といわれています。これをネギと一緒にうどんにのせたものが、ぼっかけうどんです。
懐かしい庶民の味で、牛スジのコリコリした食感がコシのあるうどんに関西風のあっさりしただしの味と相性抜群で、よいアクセントになっています。
神戸市長田区が発祥といわれ、店ごとに甘辛く煮たりあっさりした味にしたり、さまざまなぼっかけうどんが楽しめます。
播州ラーメン
播州(ばんしゅう)ラーメンは西脇市のご当地ラーメンで、細い縮れ麺と甘い醤油味のスープが特徴です。
鶏ガラや豚骨のほか、玉ねぎやりんご、さらに氷砂糖を加えて熟成させたスープで、甘いのに後味はさっぱりしていてコクもあります。
かつて西脇市は繊維業が盛んで若い女性工員がたくさん働いていたため、その女性たちが好んだ甘くてあっさりしたコクのあるスープが作られたといわれています。
ちょぼ汁
ちょぼ汁はもち粉の団子、ささげ豆、ズイキ(里芋の茎)を味噌とだし汁で煮たもので、淡路島の伝統的な郷土料理です。おしるこに似ていますが甘くありません。
栄養価が高いもち粉やささげ豆に、血液がきれいになるとされるズイキが入ったちょぼ汁は、出産した娘の体力を回復するために母親が作っていた習慣があります。
また、「子どもが可愛いおちょぼ口になるように」という願いから「ちょぼ汁」と名付けられたとされ、出産のお祝いに集まった親戚や近所に振る舞う習慣もありました。
高砂にくてん
高砂(たかさご)にくてんは生地を半分に折ったお好み焼きです。生地を薄くのばしてジャガイモ、すじ肉、こんにゃく、キャベツなどをのせて焼き、半分に折ったものを「にくてん」と呼んでいます。
すじ肉と天かすが入っているから「にくてん」と呼ばれるようになったといわれていますが真偽は不明です。第二次世界大戦後に小麦粉がアメリカから輸入されるようになってから盛んに作られるようになりました。
一般家庭では、おでんを食べた翌日に残った具材を使ってにくてんを作ることもあるようです。
牛スジの煮もの
牛スジの煮ものは関西人のソウルフードともいわれる庶民の味です。茹でてアクを取った牛スジを酒だけで炊いて、醤油で味付けした調理法がよく知られています。
関東ではモツがよく使われますが、関西では牛スジを使う料理が一般的です。関西の牛スジは串に刺したおでんの具や、こんにゃくと一緒に甘辛く煮た「ぼっかけ」が人気ですが、シンプルな煮ものもよく作られます。
山椒の佃煮
山椒(さんしょう)は和食の味付けで多く使われる香辛料の一種ですが、醤油、酒、みりんなどの調味料で佃煮にするのも山椒の代表的な食べ方です。
兵庫に伝わるのは朝倉山椒と有馬山椒で、朝倉山椒は養父市八鹿町朝倉で栽培されています。枝にトゲがなく大きい粒で香りのよいのが特長で、昭和40年ごろまでは家庭でも佃煮にして食べていましたが、昭和50年以降は香辛料として使われています。
有馬山椒は枝に鋭いトゲがあり、柑橘系の香りで辛味が強いです。現在市場に出回るのはほとんど朝倉山椒で、近年有馬山椒を復活させるプロジェクトが始まり、農家での栽培も始まっています。
ゆで松葉ガニ
松葉ガニとは山陰地方でいうズワイガニのことです。但馬(たじま)地域の名産品で、茹でて酢と醤油の二杯酢につけながら食べるのが一般的ですが、炊き込みごはん、雑炊、味噌汁、コロッケなどにも利用されています。
浜坂漁港では、毎年カニ漁の解禁シーズンに「かに祭り」が開催されています。松葉ガニを販売したりカニ汁を無料配布したりするイベントです。
松葉ガニは乱獲された時期もありましたが、近年は資源保護のため、捕獲数や漁期が制限されています。
ハモすき
ハモすきは淡路島の名物料理で、ハモと淡路島産の玉ねぎをだし汁で煮込んだ鍋料理です。
淡路島のハモは、おなかの皮が薄くて柔らかく、コクがあって肉質もよいとされています。
旬は初夏以降で、秋の産卵に向けて脂がのり「夏の風物詩」といわれます。同じころ、淡路島産の玉ねぎも収穫時期を迎えます。ハモすきは、ハモと玉ねぎの甘味がだし汁との相性が抜群の郷土料理です。
現在淡路島では若者に支持されるハモの聖地を目指し、ふるさと納税の返礼品にハモすきのセットを提供したり、ハモ料理の新商品開発に取り組んだりしています。
焼きアナゴ
焼きアナゴはアナゴを開いて串に刺し、醤油やみりんなどで作ったたれをつけて焼いたものです。
兵庫ではウナギよりもアナゴが食べられています。播磨灘は国内でも有数のアナゴの水揚げ高を誇り、身が柔らかく脂がのったアナゴがとれます。
現在も、年末年始や節分などの行事には欠かせない料理です。贈答品としても喜ばれ、家庭では焼きアナゴを巻き寿司やちらし寿司の具材としても使われています。
もちむぎ麺
もちむぎ麺は「もち麦」を使った麺で、見た目はそばのようですが独特のコシの強さと香ばしさが特徴です。
もち麦は大麦の一種で、食物繊維が多く粘り気があり、ぷちぷちとした食感があります。播磨福崎はもち麦の産地として有名で、麺のほか、おかきやお茶などにも加工されています。
夏は冷たいざる麺として、冬は温かい煮込みにしても煮くずれしにくく、パスタの麺としても食べてもおいしいです。
じゃぶ
じゃぶとは鶏肉と豆腐、野菜、糸こんにゃくなどを煮て作る、家庭料理です。
煮物ですが水を使わず、豆腐や野菜から出た水分でじゃぶじゃぶすることから「じゃぶ」と名付けられたといわれています。
じゃぶは肉が手に入りにくかった時代のごちそうで、祭りやお盆、冠婚葬祭などの行事の際には、大鍋で作って振る舞われました。現在も観光イベントで提供されるほか、「地域らしさ」と「新しさ」を兼ね備えた商品が選定される「五つ星ひょうご」としてレトルトパックが販売されています。
はたはたの唐あげ
はたはたの唐あげは但馬地域に伝わる郷土料理で、ハタハタの頭と内臓を取り除いて丸ごと油で揚げたものです。
但馬地域は全国有数のハタハタの漁獲量を誇ります。
ウロコがなくて身がはがれやすく、調理しやすく味にもクセがありません。但馬地域の家庭料理として唐あげや、煮付けにしたり干して焼いて食べたりもされています。
但馬地域の小学校では給食のメニューとして提供されるほか、児童が実際にはたはたの唐あげを作る体験学習も実施されています。
やたら漬け
やたら漬けは「やたら野菜を使って、やたらおいしい」ことから名付けられた冬の保存食です。
なす、きゅうり、しその実、みょうがなど何種類もの野菜を半年かけて漬け込みます。いっぺんに漬けるのではなく、収穫時期ごとに漬け物桶に塩漬けにするのが特徴で、11月ごろ塩抜きして粗く刻み、数日間調味液に漬け込んで完成します。
現在は作る人が減って、購入は難しくなりました。播磨の一部の家庭で作られるのみとなっています。
味噌だれ餃子
味噌だれ餃子は神戸で好まれる餃子の食べ方で、一般的な酢醤油とラー油ではなく、味噌だれにつけて食べます。市内の中華料理店やラーメン店には味噌だれが置いてあり、味噌だれ餃子が食べられます。
第二次世界大戦前に満州に住んでいた日本人の間では焼き餃子が好まれ、日本を懐かしんで味噌をつけて食べる家庭が多くありました。
大戦後、満州から引きあげた男性が開いた飲食店で餃子に味噌だれをつけて提供したところ話題になったといわれています。
2014年には、味噌だれ餃子の元祖と言われる店「ぎょうざ苑」の餃子が兵庫県の「五つ星ひょうご」にも選定されています。
たこめし
兵庫の播磨灘は、日本有数のタコの漁獲量で知られています。海の流れが速い明石海峡で育ったタコは身に弾力があり「陸でも立って歩く」といわれるほど力強いです。
たこめしは米にだし汁と調味料を合わせ、タコを入れて炊いたもので、漁のあとでも下ごしらえの手間がかからないためよく作られていました。
現在は家庭でも作られるようになり、生ダコのほか煮ダコ、干ダコを使ったたこめしも親しまれています。
いびつもち
いびつもちは全国的には「かしわ餅」と呼ばれるもので、餅の中にあんを入れてサルトリイバラの葉で包んだものです。
いびつもちも、かしわ餅同様、端午の節句に作られてきましたが、兵庫には柏の葉があまり自生しておらずサルトリイバラの葉が使われました。葉の形がいびつなため「いびつもち」と名が付いたといわれています。
淡路では「いびつもち」ですが、神戸では「柏餅」、北播磨は「ひょっとで」、西播磨では「ばたこ」と呼ばれています。
兵庫の郷土料理の特徴

兵庫は日本でも有数の大都市・神戸市があり、世界文化遺産に登録された姫路城や甲子園球場など、人気スポットが非常に豊富です。
そんな兵庫の郷土料理の特徴は、次のとおりです。
- 国際貿易港として独自の文化が発展
- 暮らしに根付いた黒豆を使った料理
順に解説します。
国際貿易港として独自の文化が発展
兵庫の神戸港が国際貿易港として栄えた理由の一つに、水深が深く満潮と干潮の差が少なく停泊しやすい上に、京都や大阪とも近い「良港」だったことが挙げられます。
神戸港の開港後、神戸には外国の文化が流入し、食の玄関口として栄えてきました。開港後、ビーフステーキのような洋食が誕生し、気軽に食べられる洋食としてかつめしも人気になりました。
洋食と和食、新旧の食文化が入り混じった兵庫は、独自の食文化が発展しています。
暮らしに根付いた黒豆を使った料理
兵庫・丹波の名産品である黒豆は、大きさや質のよさから黒大豆の最高級と評価されています。現在でも祭りでは黒豆が配られ、黒豆ごはんにして家族で食べる風習があり、黒豆は兵庫の暮らしに根付いています。
丹波の黒豆は江戸時代、用水不足のために稲作をしない田んぼで黒豆を栽培するようになり、令和3年には栽培方法が日本農業遺産に認定されました。
兵庫の郷土料理をもっとおいしく食べるための味付けのポイント

兵庫は瀬戸内海と日本海に囲まれ、国際貿易港として栄えた神戸港もあって水産物が有名ですが、畜産や農産も盛んでさまざまな食材があります。
「兵庫の郷土料理を自分でも作って味わってみたい!」という人も多いでしょう。
兵庫の郷土料理をおいしく作るなら、ぜひ調味料にこだわりましょう。なぜなら、調味料は料理の味を大きく左右するからです。
鰹節専門店にんべんは300年以上前から和食の味を支えてきました。プロの料理人からも高く評価されるにんべんの調味料を使えば、兵庫の郷土料理をさらにおいしく味付けできます。
「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」は木桶の中でゆっくり熟成させた本格醤油です。
▶「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」はこちら
国産の材料のみを使った醤油をぜひ味わってみてください。
「白だしゴールド 500mll」は香り高く味わい豊かな料理を簡単に作れます。
▶にんべんの「白だしゴールド 500ml」はこちら
有機栽培の大豆と小麦で作った本醸造有機醤油を使用しているので、食材の味を引き立てることが可能です。
「本枯鰹節薫る味だし(かつお・昆布)」は関西風の料理に欠かせない昆布だしと本格的なかつおの合わせだしが手軽にひけます。
▶にんべんの「本枯鰹節薫る味だし(かつお・昆布)」はこちら
沸騰したお湯にパックを1つ入れるだけで合わせだしがひけます。
まとめ:兵庫の郷土料理を自宅でも味わいましょう
兵庫は大都市神戸があり、世界的に有名な観光地も多い土地でありながら海の幸に農産物や畜産物などの食材が豊富な土地です。
「兵庫で食べた郷土料理を自宅でも作って味わってみたい!」という人も多いでしょう。
兵庫の郷土料理をよりおいしく作るなら、ぜひ調味料にこだわりましょう。よい調味料を使うだけで、料理の味付けが簡単にできます。
もう一度、和食の味を300年以上支えてきた鰹節専門店にんべんの調味料を紹介します。
「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」は食のプロも使用する本格醤油です。
▶「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」はこちら
濃厚な味わいで料理を食べる人の舌を楽しませてくれます。
「白だしゴールド 500ml」は、だし素材をレギュラー品の1.5倍使っているので、豊かなだしの味わいを感じられるでしょう。
▶にんべんの「白だしゴールド 500ml」はこちら
関西風の淡色仕立ての料理を作るときに特に役に立ちます。
「本枯鰹節薫る味だし(かつお・昆布)」は沸騰したお湯にだしパックを入れるだけの手軽さでだしがひけます。
▶にんべんの「本枯鰹節薫る味だし(かつお・昆布)」はこちら
本格的な合わせだしを自宅でも味わえます。
にんべんの調味料を使って、兵庫の郷土料理を自宅でおいしく手軽に味わってください。
 公式ネットショップ
公式ネットショップ