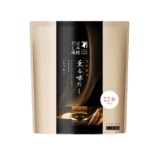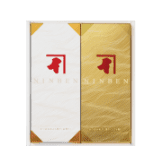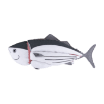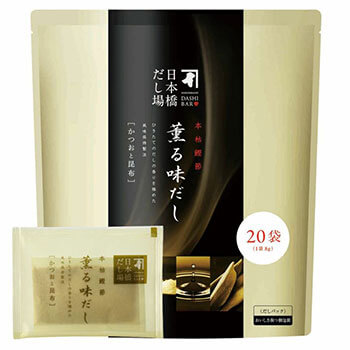食用きのこの種類一覧!栄養や上手な選び方や調理・保存方法・レシピを紹介
最終更新日:
公開日:

「きのこにはどんな種類があるの?」
「きのこにはどんな栄養があるのだろう」
「きのこの上手な選び方や調理・保存方法を理解して、効率良く栄養を摂りたい」
さまざまな料理に使いやすいきのこですが、改めて種類や栄養についてを知りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、きのこの主な種類一覧や栄養、調理・保存方法などをまとめました。
最後には、きのこを使ったオリジナルレシピも紹介しています。
最後まで読めば、きのこの種類、きのこが持つ豊富な栄養と、栄養を逃さずおいしく食べる方法について理解できます。ぜひご一読ください。
目次
- きのこの種類は4,000~5,000種類
- 食用きのこの種類一覧
- 胞子の作り方別のきのこの分類
- 栄養の摂り方別のきのこの分類
- きのこの主な栄養一覧
- きのこの栽培方法の違い
- 菌床栽培(きんしょうさいばい)
- 原木栽培(げんぼくさいばい)
- きのこの選び方は?
- きのこの調理方法は?加熱しても大丈夫?
- きのこの保存方法は?
- きのこのオリジナルレシピ【1】「3種のきのこと豆乳クリームの全粒粉パスタ」
- きのこのオリジナルレシピ【2】クミン香る きのこのさっぱりマリネ
- きのこのオリジナルレシピ【3】「ごま香る えのきたけ玄米焼きおにぎり」
- きのこをおいしく食べたいなら調味料にもこだわりましょう
- まとめ:きのこをおいしく食べて栄養を摂りましょう!
きのこの種類は4,000~5,000種類

「きのこにはどのくらいの種類があるの?」と疑問に思っている人もいるでしょう。
林野庁の発表によると、きのこの種類は「4,000~5,000種類」といわれています。詳しい内訳は、以下のとおりです。
- 全体:4,000~5,000種類
- 食用きのこ:約100種類
- 毒きのこ:200種類以上
食用きのこと毒きのこ以外の約3,700~4,700種類のきのこについては、食用にできるのか、毒があるのかは不明です。
また、「色鮮やかなら毒きのこ」、「虫が食べているなら食用きのこ」などの見分け方で毒きのこか食用きのこかわかるといわれてきましたが、根拠はありません。毒きのこか食用きのこか、安易に自分で判断しないようにしましょう。
食用のきのこは約100種類以上あるため、さまざまなきのこを楽しめるでしょう。
食用きのこの種類一覧

きのこは日本国内に数千種類あるといわれています。
ここでは、そのなかから主要なものを14種類ピックアップしてご紹介します。
- えのきたけ
- エリンギ
- まいたけ
- ぶなしめじ
- しいたけ
- なめこ
- 松茸
- マッシュルーム
- きくらげ
- ひらたけ
- ブナハリタケ
- ポルチーニ
- トリュフ
- ふくろ茸
それでは一つずつ見ていきましょう。
えのきたけ

えのきたけはタマバリタケ科のきのこの一種で、きのこのなかでもビタミンB1が含まれています。えのきたけのシャキシャキとした食感を好む人も多いのではないでしょうか。
なめ茸にしたり鍋や味噌汁、ハンバーグに入れたりと、さまざまな食材との組み合わせを楽しめるのも特長です。
エリンギ

エリンギは、ヒラタケ科のきのこの一種で、食物繊維やカリウムが多く含まれています。
歯応えが良く、手頃な価格の食材です。バターと合わせて炒めたりパスタの具材に使用したりと、さまざまな料理で役立ちます。
まいたけ

まいたけはトンビマイタケ科のきのこの一種で、きのこのなかでもビタミンDやβ(ベータ)グルカンが多く含まれています。
旨味の強さや歯切れの良さが特徴です。天ぷらや炊き込みご飯など、幅広い料理で楽しめます。
ぶなしめじ

ぶなしめじはシメジ科の一種で、β(ベータ)グルカンが多く含まれています。また、しめじは肝臓の働きを助けるとされているオルニチンが豊富で、二日酔いの予防や疲労回復も期待できます。
しめじはパスタや炊き込みご飯に重宝され、冷凍により旨味が増してよりおいしくなります。
しいたけ

しいたけはキシメジ科の一種で、乾燥させると、生で食べるよりもタンパク質やリン、ビタミンDや食物繊維などを多く含むようになります。
旨味成分も豊富で、だしや天ぷらなどさまざまな料理に活かせます。沢山あるきのこのなかでも、日本人の知名度や人気が高いきのこです。不足しがちな栄養を補えるうえ、低カロリーのため、ダイエットにも向いています。
なお、しいたけに関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。
しいたけは栄養が豊富?効果・効能、おいしく食べるコツや保存方法を解説
なめこ

なめこはモエギタケ科の一種で、他のきのこと比較してカロリーが低いです。ぬめりがあるのが特徴で、味噌汁やおひたしなどに使われます。
洗い過ぎると旨味や栄養が流れ出てしまうため、軽く洗うようにしましょう。
松茸

松茸はキシメジ科の一種で、きのこのなかでもナイアシンが多く含まれています。香りや風味の良さが特徴で、松茸ご飯や土瓶蒸しなどに使われる食材です。
日本国内では「秋に楽しめる高級食材」としても知られています。
マッシュルーム(ツクリタケ)

マッシュルームはハラタケ科の一種で、きのこのなかでもカロリーが低いです。消費量・生産量ともに世界で最も多いきのことされています
生で食べることもでき、シチューやソテーなど幅広い料理で使われます。別名「ツクリタケ」とも呼ばれます。
きくらげ

きくらげはキクラゲ科の一種で、乾燥させると生で食べるよりもカルシウムやビタミンD、食物繊維などが摂れるようになる食材です。弾力のある歯応えで、ラーメンやスープ、炒め物などさまざまな料理に使われます。
食感がクラゲに似ていることから、「きくらげ」と呼ばれています。
ひらたけ

ひらたけはヒラタケ科の一種で、漢字では「平茸」と書きます。その名のとおり、傘が平べったい見た目をしています。
ひらたけはしっかりとした弾力を持っており、クセの少ない香りや味わいをしているので、炊き込みご飯、パスタなど幅広い料理に使いやすいです。
寒い季節(12月~2月)に発生することが多いため、別名「カンタケ(寒茸)」とも呼ばれています。
ブナハリタケ

ブナハリタケはエゾハリタケ科の一種です。傘の裏に針状の突起があり、漢字で「橅針茸」と書きます。
まろやかな味わいとしっかりした食感があるため、天ぷらや鍋物、炊き込みご飯に使われます。
ポルチーニ

ポルチーニはハラタケ目イグチ科の一種です。
濃厚な香りが特徴で、イタリア料理ではよく使われています。強い旨味にほどよい弾力を持っており、食べると舌を楽しませてくれます。
トリュフ

トリュフは子嚢菌類セイヨウショウロ属に属するきのこです。
キャビアとフォアグラとともに「世界三大珍味」とされ、なおかつ、松茸とポルチーニとともに「世界三大きのこ」とも称されるトリュフ。
非常に上品で豊かな香りと、濃厚な味が特長です。トリュフを添えるだけで、料理の味が大きく変わります。
ふくろ茸

ふくろ茸はハラタケ目ウラベニガサ科の一種です。漢字では「袋茸」と書きます。その名のとおり、一般的な形のきのこが袋に覆われているような見た目をしています。
中国が原産で、アジアで広く栽培されているため、中華料理やタイ料理で広く使われます。やわらかい食感と独特の旨味を持つきのこです。
胞子の作り方別のきのこの分類

きのこは繁殖に必要な胞子の作り方によって、次の2つに分けられます。
- 担子菌類(たんしきんるい)
- 子嚢菌類(しのうきんるい)
順番に解説していきます。
担子菌類(たんしきんるい)
担子菌類(たんしきんるい)とは「担子器(たんしき)」という器官の外側で胞子を作るきのこです。
松茸やしいたけは、担子菌類のきのこです。
子嚢菌類(しのうきんるい)
子嚢菌類(しのうきんるい)とは「子嚢(しのう)」という袋状の器官の中で胞子を作るきのこです。
トリュフやアミガサタケが子嚢菌類のきのこに属します。
栄養の摂り方別のきのこの分類

きのこは栄養の摂り方によって、次の2つに分けられます。
- 菌根性(きんこんせい)
- 腐生性(ふせいせい)
それぞれ解説していきます。
菌根性(きんこんせい)
菌根性(きんこんせい)は生きている植物と共生して栄養を摂ります。
菌糸を植物の根に伸ばして、菌根を作ります。きのこは植物から糖類を吸収する代わりに、カリウムやリンなどの無機物を植物に送ります。
松茸やトリュフが菌根性に該当します。
腐生性(ふせいせい)
腐生性(ふせいせい)は倒木、切り株や落ち葉に生えて、植物の有機物(セルロースやリグニン)を吸収して成長するきのこです。
腐生性によって分解された木や落ち葉は土に帰っていきます。しいたけ、なめこやマッシュルームが腐生性に属するきのこです。
しいたけ、なめこは木の幹を分解する「木材腐朽(ふきゅう)菌」、マッシュルームは落ち葉を分解する「落葉分解菌」を持っています。
きのこの主な栄養一覧

きのこはヘルシー食材としても知られており、血液をサラサラにする効果や丈夫な骨作り、メタボ予防などが期待できます。
また、免疫力を高めるとされる栄養素も含まれています。
ここでは、きのこの主な栄養について、以下のものを紹介します。
- タンパク質
- カルシウム
- リン
- ビタミンB群
- ビタミンD
- 食物繊維
- β(ベータ)グルカン
それでは一つずつ見ていきましょう。
なお、以下のきのこについては、日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に記載がないため、含有量を記載していません。
- ブナハリタケ
- ポルチーニ
- トリュフ
- ふくろ茸
タンパク質
タンパク質はエネルギー産生栄養素の一つです。
体の細胞を構成する主要な成分であるため、生命維持に欠かせない非常に重要な栄養素とされています
| タンパク質(可食部100gあたりの成分値) | |
|---|---|
| えのきたけ | 2.7g |
| エリンギ | 2.8g |
| まいたけ | 2.0g |
| ぶなしめじ | 2.7g |
| しいたけ(乾) | 21.2g |
| なめこ | 1.8g |
| 松茸 | 2.0g |
| マッシュルーム | 2.9g |
| きくらげ(乾) | 7.9g |
【出典】:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
きのこ類を食べることでタンパク質も摂取でき、特にしいたけ(乾)には100gあたり21.2gと豊富に含まれています。
カルシウム
カルシウムは、体内に最も多く含まれるミネラルです。
歯や骨を構成する主要な成分であり、他にも細胞分裂に関与したり、血が固まる作用を促進したりする働きがあるとされています。
| カルシウム(可食部100gあたりの成分値) | |
|---|---|
| えのきたけ | 微量 |
| エリンギ | 微量 |
| まいたけ | 微量 |
| ぶなしめじ | 1mg |
| しいたけ(乾) | 12mg |
| なめこ | 4mg |
| 松茸 | 6mg |
| マッシュルーム | 3mg |
| きくらげ(乾) | 310mg |
【出典】:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
カルシウムが摂取できるきのこ類もあり、特にきくらげ(乾)では100gあたり310mgものカルシウムが含まれています。なお、カルシウムはタンパク質やビタミンDと一緒に摂ると吸収率が上がるとされており、タンパク質やビタミンDも含まれているきのこは優れた食材といえるでしょう。
リン
リンは歯や骨の発達に必要な栄養素で、他にもエネルギー代謝や神経伝達などに関与しているといわれています。
カルシウム同様に歯や骨を構成する成分です。
| リン(可食部100gあたりの成分値) | |
|---|---|
| えのきたけ | 110mg |
| エリンギ | 89mg |
| まいたけ | 54mg |
| ぶなしめじ | 96mg |
| しいたけ(乾) | 290mg |
| なめこ | 68mg |
| 松茸 | 40mg |
| マッシュルーム | 100mg |
| きくらげ(乾) | 230mg |
【出典】:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
きのこ類を食べることでリンも摂取でき、特にしいたけ(乾)には100gあたり290mg含まれています。
カルシウムを摂らずにリンだけを多く摂る生活を続けた場合、骨量や骨密度が下がることがあります。しかし、きのこはカルシウムも摂取できるため、問題ないでしょう。
ビタミンB群
ビタミンB群は、糖質や脂質・タンパク質をエネルギー変換する際に欠かせない栄養素です。
ビタミンB群を構成する栄養素には、ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンの8種類があります。
| ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | ナイアシン | パントテン酸 | 葉酸 | ビオチン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えのきたけ | 0.24mg | 0.17mg | 0.12mg | 0 | 6.8mg | 1.40mg | 75μg | 11.0μg |
| エリンギ | 0.11mg | 0.22mg | 0.14mg | 0 | 6.1mg | 1.16mg | 65μg | 6.9μg |
| まいたけ | 0.09mg | 0.19mg | 0.06mg | 0 | 5.0mg | 0.56mg | 53μg | 24.0μg |
| ぶなしめじ | 0.15mg | 0.17mg | 0.09mg | 0.1μg | 6.1mg | 0.81mg | 29μg | 8.7μg |
| しいたけ(乾) | 0.48mg | 1.74mg | 0.49mg | ー | 19.0mg | 8.77mg | 270μg | 41.0μg |
| なめこ | 0.07mg | 0.12mg | 0.05mg | 微量 | 5.3mg | 1.29mg | 60μg | 7.4μg |
| 松茸 | 0.10mg | 0.10mg | 0.15mg | 0 | 8.0mg | 1.91mg | 63μg | 18.0μg |
| マッシュルーム | 0.06mg | 0.29mg | 0.11mg | 0 | 3.0mg | 1.54mg | 28μg | 11.0μg |
| きくらげ(乾) | 0.19mg | 0.87mg | 0.10mg | 0 | 3.2mg | 1.14mg | 87μg | 27.0μg |
※いずれも可食部100gあたりの成分値
【出典】:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
きのこ類には、他の野菜と比較してビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシンなどのビタミンB群が比較的多く含まれています。
食材をエネルギーに変える働きがあるため、疲れている人は積極的に摂取するとよいでしょう。また、ビタミンB2は身体の発育には欠かせないものであり、特に子供には積極的に摂らせたい栄養素です。
ビタミンD
ビタミンDは、血中カルシウム濃度や血中リン濃度を正常に保つ働きが期待されています。
| ビタミンD(可食部100gあたりの成分値) | |
|---|---|
| えのきたけ | 0.9μg |
| エリンギ | 1.2μg |
| まいたけ | 4.9μg |
| ぶなしめじ | 0.5μg |
| しいたけ(乾) | 17.0μg |
| なめこ | 0 |
| 松茸 | 0.6μg |
| マッシュルーム | 0.3μg |
| きくらげ(乾) | 85.0μg |
【出典】:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
ビタミンDはまいたけやしいたけ(乾)などで多く摂取でき、特にきくらげ(乾)には豊富なビタミンDが含まれています。しいたけは、生では0.3μgですが、干すことでビタミンDが増えます。
ビタミンDは免疫力を高める働きもあるとされるため、元気よく過ごしたい人にはおすすめです。
食物繊維
食物繊維は、食後の血糖値上昇を抑えたり腸内環境を改善したりする働きがあるといわれています。
食物繊維は、糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルとあわせた、6大栄養素のうちの一つです。
| 食物繊維(可食部100gあたりの成分値) | |
|---|---|
| えのきたけ | 3.9g |
| エリンギ | 3.4g |
| まいたけ | 3.5g |
| ぶなしめじ | 3.0g |
| しいたけ(乾) | 46.7g |
| なめこ | 3.4g |
| 松茸 | 4.7g |
| マッシュルーム | 2.0g |
| きくらげ(乾) | 57.4g |
【出典】:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
きのこ類は食物繊維を多く摂れる食材として知られており、特にしいたけ(乾)やきくらげ(乾)には豊富に含まれています。
食物繊維が不足すると有害物質が腸内にたまって腸内環境が悪化する恐れがあるため、積極的に摂るのがおすすめです。
β(ベータ)グルカン
β(ベータ)グルカンは、免疫力を強化したり、コレステロール値の上昇を抑えたりする効果があるといわれています。
また、腸内環境改善等も期待できる栄養素です。日本食品標準成分表2020年版(八訂)にはβ(ベータ)グルカンに関する記載はないものの、きのこはβ(ベータ)グルカンが多く摂れる食材として知られています。特に、えのきたけ、まいたけやエリンギなどで豊富です。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構では、きのこ別のβ(ベータ)グルカンを以下のように発表しています。
| β(ベータ)グルカン(100gあたりの成分値) | |
| えのきたけ | 1.4g |
| エリンギ | 1.3g |
| まいたけ | 1.8g |
| ぶなしめじ | 0,8g |
| しいたけ | 0.8g |
| なめこ | 1.2g |
| マッシュルーム | 0g |
| きくらげ(乾) | 0g |
参考:農研機構|国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
β(ベータ)グルカンを多く含む食材は多くないため、きのこはβ(ベータ)グルカンが摂れる貴重な食材の一つです。ただし、マッシュルームやきくらげのように、β(ベータ)グルカンを含まないきのこもあります。
きのこの栽培方法の違い

きのこの栽培方法には、主に次の2種類があります。
- 菌床栽培(きんしょうさいばい)
- 原木栽培(げんぼくさいばい)
それぞれ解説していきます。
菌床栽培(きんしょうさいばい)
菌床栽培(きんしょうさいばい)とは、室内できのこを育てる方法です。
細かい木材と米ぬかで作ったブロック状のもの(菌床)に種菌を入れて、きのこを育てます。
建物内で温度や湿度を管理することで、1年中きのこを出荷できます。害虫の心配も少ないため、国内で生産されているきのこは90%以上が菌床栽培とされています。
原木栽培(げんぼくさいばい)
原木栽培(げんぼくさいばい)とは、森の中の木できのこを育てる方法です。
原木(ほぼ伐採した木)に穴を開け、種菌を入れて、きのこを育てます。
収穫するまで1~2年かかる場合もあり、自然のなかで育てるため、収穫できるのは、1年のうち春と秋の2回だけです。また、菌床栽培に比べると害虫の被害がでやすいです。
しかし、時間をかけて育てる分、「原木栽培は菌床栽培よりも香りや味が豊かになりやすい」といわれています。
きのこの選び方は?

この章では、きのこを選ぶ際のポイントを紹介します。
- かさが開ききっていないものを選ぶ
- 水っぽいものは避ける
- かさの裏側の色が白いものを選ぶ
きのこの状態によっては、鮮度が低かったり、風味や味が落ちていたりするものもあります。
きのこの選び方を間違えないために、ぜひ参考にしてください。
かさが開ききっていないものを選ぶ
特にしいたけを選ぶ際には、かさが開ききっていないものがおすすめです。
また、傷が付いていない肉厚なものを選ぶとよいでしょう。きのこ自体に弾力があると新鮮な証拠です。
水っぽいものは避ける
水っぽいものは古くなり、鮮度も下がっているため、避けるのが無難です。
きのこは水に触れたら味や香りが落ちてしまいます。パッケージを手に取る際は、中に水滴がないかを確認しましょう。
かさの裏側の色が白いものを選ぶ
かさの裏側の色が白いのは、きのこが新鮮である証拠です。かさにハリやツヤがあるものなら、より新鮮です。
逆にかさの裏側が変色してハリやツヤがないきのこの場合、古くなっていることが多いです。
きのこの調理方法は?加熱しても大丈夫?

きのこを調理する際は、栄養を落とさずおいしく食べられる方法を選びたいところです。ここでは、きのこの調理で気をつけるべきポイントをご紹介します。
- 種類によっては乾燥させる
- 水洗いしてよいものと避けたほうがよいきのこがある
- 加熱時間に気を配る
ぜひ覚えておきましょう。
種類によっては乾燥させる
きのこの種類によっては、乾燥させたほうがよいものもあります。
たとえば、しいたけの場合、乾燥によって栄養価を高めることができます。しいたけは乾燥させるとグアニル酸が増えるためです。
水洗いしてよいものと避けたほうがよいきのこがある
汚れを気にして水洗いしたがる人もいるようですが、水洗いしてよいかどうかはきのこの種類によって異なります。
調理でよく使われるきのこのなかで水洗いしてよいものは、マッシュルーム・なめこぐらいです。水洗いすることで栄養や風味が失われてしまうため、その他のきのこでは基本的に水洗いは不要です。
汚れが気になる場合は、キッチンペーパーで軽く拭いて取り除きましょう。ただし、スーパーで販売されているきのこは、基本的に清潔なため、何もしなくてもそのまま調理できます。
加熱時間に気を配る
きのこは香りを楽しめることも特長ですが、加熱時間が長いとせっかくの香りを逃がしてしまう恐れがあります。
炒めたり煮込んだりする際には、加熱時間に気を配るようにしましょう。火の通りにくい食材から先に加熱して、きのこはあとから加熱するのがおすすめです。
きのこの保存方法は?

きのこの保存は保存袋に入れ、封をした状態で冷凍するのがベストとされています。
冷凍すると細胞が破壊されやすくなり、香りや旨味の成分が増しておいしくなるからです。冷凍保存する際は、あらかじめ調理しやすいサイズにカットしておくとよいでしょう。
また、しめじやまいたけ・エリンギなどは湿気を嫌がるため、冷蔵保存する際には気をつけてください。ペーパータオルで包み、ポリ袋に入れることで湿気を避けられます。
えのきたけは、立てた状態のまま野菜室で保存するのがおすすめです。
冷蔵保存の場合は最長1週間程度、冷凍保存の場合は最長1ヵ月程度で食べきるようにしましょう。
次に、きのこを使ったオリジナルレシピを紹介します。
きのこのオリジナルレシピ【1】「3種のきのこと豆乳クリームの全粒粉パスタ」

調理時間:20分 材料2人前
- 全粒粉パスタ(違う種類のパスタでも可能) 160g
- 湯 2L
- 塩 20g (湯1Lに対し1%の塩)
- まいたけ 1袋
- しめじ 1/2袋
- えのきたけ 1/2袋
- 有塩バター 20g
(ソース)
- つゆの素ゴールド 大さじ2
- 無調整豆乳 150ml
(トッピング)
- 粉チーズ 適量
- 粗挽き黒胡椒 適量

作り方
1.大きめの鍋に湯を沸かし、沸騰したら塩、全粒粉パスタを入れ記載の茹で時間より1分短く茹でる。
2.まいたけは手でほぐす。しめじは石づきを切り落とし、手でほぐす。えのきたけは石づきを切り落とし、半分に切り、手でほぐす。
3.中火に熱したフライパンに有塩バターを入れ、溶けたら2のきのこ類を2分ほど炒める。きのこがしんなりしたら、(ソース)を入れる。ふつふつとしてきたら1のパスタを加え、全体が混ざったら火から下ろす。器に盛り付け、粉チーズと粗挽き黒胡椒をふりかける。

栄養価
1人前あたり エネルギー565kcal タンパク質20.7g 脂質14.1g 炭水化物88.7g 食塩相当量5.7g
ポイント1
全粒粉パスタは、茹ですぎに注意してください。茹でたあと、さらにフライパンで加熱をするため、余熱でどんどん火が入り柔らかくなってしまいます。
また、全粒粉パスタとソースを和えるときはトングを使用すると混ぜやすいです。
ポイント2
きのこは、ビタミンB1を含んでいます。炭水化物を分解してエネルギーに変える際に働き、代謝をスムーズにするとされています。不足すると炭水化物をエネルギーに変えられず、肥満につながりやすくなるうえ、疲労も感じやすくなります。
今回のレシピで例えると、パスタのみでは炭水化物が主になってしまいます。しっかりとエネルギー代謝をさせるためにも、きのこ類をたっぷり入れたレシピにしています。
きのこのオリジナルレシピ【2】クミン香る きのこのさっぱりマリネ

調理時間:10分 材料:4人前
- しめじ 1袋
- えのきたけ 1袋
- オリーブオイル 大さじ1
(合わせ調味料)
- 本枯鰹節 だし入りポン酢 大さじ1.5
- 酒 大さじ3
- 水 50ml
- 粒マスタード 大さじ1
- クミンパウダー 小さじ½
- 塩 ふたつまみ
- 黒こしょう 少々
(トッピング)
- イタリアンパセリ(パセリでも代用可)適量

作り方
1.しめじとえのきたけは、石づきを切り落とし手でほぐす。
2.ボウルに合わせ調味料を入れ、よく混ぜる。

3.中火に熱したフライパンに、オリーブオイルと1を入れて2分ほど炒める。
4.きのこ類がしんなりしたら、2の調味料を入れる。汁気がなくなるまで炒め、火からおろす。好みでイタリアンパセリを散らす。

栄養価
1人あたり エネルギー59kcal タンパク質2.0g 脂質4.1g 炭水化物3.4g 食塩相当量 1.5g
ポイント1
調味料(酒含む)を入れる際は、フライパンにスペースを作ってから加えるとアルコールを上手に飛ばすことができます。アルコールを飛ばす前に全体に混ぜ合わせてしまうと、きのこにアルコールのにおいが移ってしまうことがあります。
ポイント2
きのこは、ビタミンB1を含んでいます。炭水化物を分解してエネルギーに変える際に働き、代謝をスムーズにするとされています。不足すると炭水化物をエネルギーに変えられず、肥満につながりやすくなるうえ、疲労も感じやすくなります。
きのこのオリジナルレシピ【3】「ごま香る えのきたけ玄米焼きおにぎり」

調理時間:10分 材料:2人前
- 玄米ごはん 200g
- えのきたけ 1/2袋
- 有塩バター 10g
- つゆの素ゴールド 大さじ1
- 白いりごま 大さじ3
- のり (縦5cm×横5cm)
トッピング用(お好みで)
- 有塩バター 5〜10g程

作り方
1.えのきたけは石づきを切り落とし、半分に切り、手でほぐす。
2.中火に熱したフライパンに有塩バターを溶かし、1を炒める。しんなりしたら、玄米ごはん、つゆの素ゴールドを入れ全体に味が馴染むように炒める。
3.ラップに2をのせて包み、おにぎり型に形成する。白いりごまを敷いたバットに、ラップを外したおにぎりをのせて全体にまぶす。


4.フライパンを強火で熱し、3の両面を2分ずつ焼く。焼き色がついたら火からおろし、お好みで有塩バターを追加し、のりを巻く。
栄養価
1人あたり エネルギー353kcal タンパク質8.1g 脂質19.3g 炭水化物36.8g 食塩相当量1.0g
ポイント1
おにぎりの焼き色はお好みで調整してください。なかなか焼き色がつかない場合は、火加減と加熱時間を長めに調整してください。
ポイント2
えのきたけは、ビタミンB1を含んでいます。炭水化物を分解してエネルギーに変える際に働き、代謝をスムーズにするとされています。不足すると炭水化物をうまくエネルギーに変えられず、肥満につながりやすくなるうえ、疲労も感じやすくなります。特に炭水化物メインの料理などには、代謝を促すためにも積極的に取り入れたい食材です。
きのこをおいしく食べたいなら調味料にもこだわりましょう

調味料にこだわると、きのこをよりおいしく食べることができます。調味料は料理の基本。特に「さしすせそ」は料理に欠かせません。
1699年創業のにんべんでは、本格的な料理が作れるようになる調味料を数多く取り揃えています。
椎茸の豊かな味わいのだしをお手軽にひけます。
「本枯鰹節 薫る味だし(かつおと昆布)8g×20袋入」は厳選した素材で作っただしパックです。
▶にんべんの「本枯鰹節 薫る味だし(かつおと昆布)8g×20袋入」はこちら
水と鍋があれば、本格的なだしをひけます。
「だしポット・削りぶし4袋セット」は、鍋を使わずに電子レンジに水と鰹節を入れるだけでおいしいだしがひける商品です。
▶にんべんの「だしポット・削りぶし4袋セット」はこちら
「鍋を使わずにだしをひきたい」というときに便利です。
にんべんの「つゆの素ゴールド」はナチュラルなおいしさが味わえます。
▶にんべんのつゆの素ゴールドはこちら
きのことの相性も抜群なので、ぜひ一度お試しください。
まとめ:きのこをおいしく食べて栄養を摂りましょう!

きのこが持つ栄養と、栄養を逃さずおいしく食べるための方法について紹介しました。
きのこはさまざまな料理で活躍する栄養たっぷりの食材です。今回お伝えしたきのこの選び方や調理・保存方法を参考に、毎日の献立にお役立てください。また、きのこをおいしく食べたいなら調味料にもこだわるとよいでしょう。
最後にもう一度、きのこ料理にもおすすめなにんべんの調味料を紹介します。
うま味が詰まっただしを取ることができます。
「本枯鰹節薫る味だし(かつおと昆布)8g×20袋入」は手軽にだしをひける便利な商品です。
▶にんべんの「本枯鰹節 薫る味だし(かつおと昆布)8g×20袋入」はこちら
高級料亭のような豊かな味わいを楽しめます。
「だしポット・削りぶし4袋セット」は電子レンジだけでだしがひける便利な商品です。
▶にんべんの「だしポット・削りぶし4袋セット」はこちら
鍋を使わないので、洗い物が少なくてすみます。
にんべんの「つゆの素ゴールド」はナチュラルな味わいで、きのこ料理におすすめの調味料です。
▶にんべんのつゆの素ゴールドはこちら
ぜひ、きのこをおいしく食べて、栄養をたくさん摂りましょう。
 公式ネットショップ
公式ネットショップ